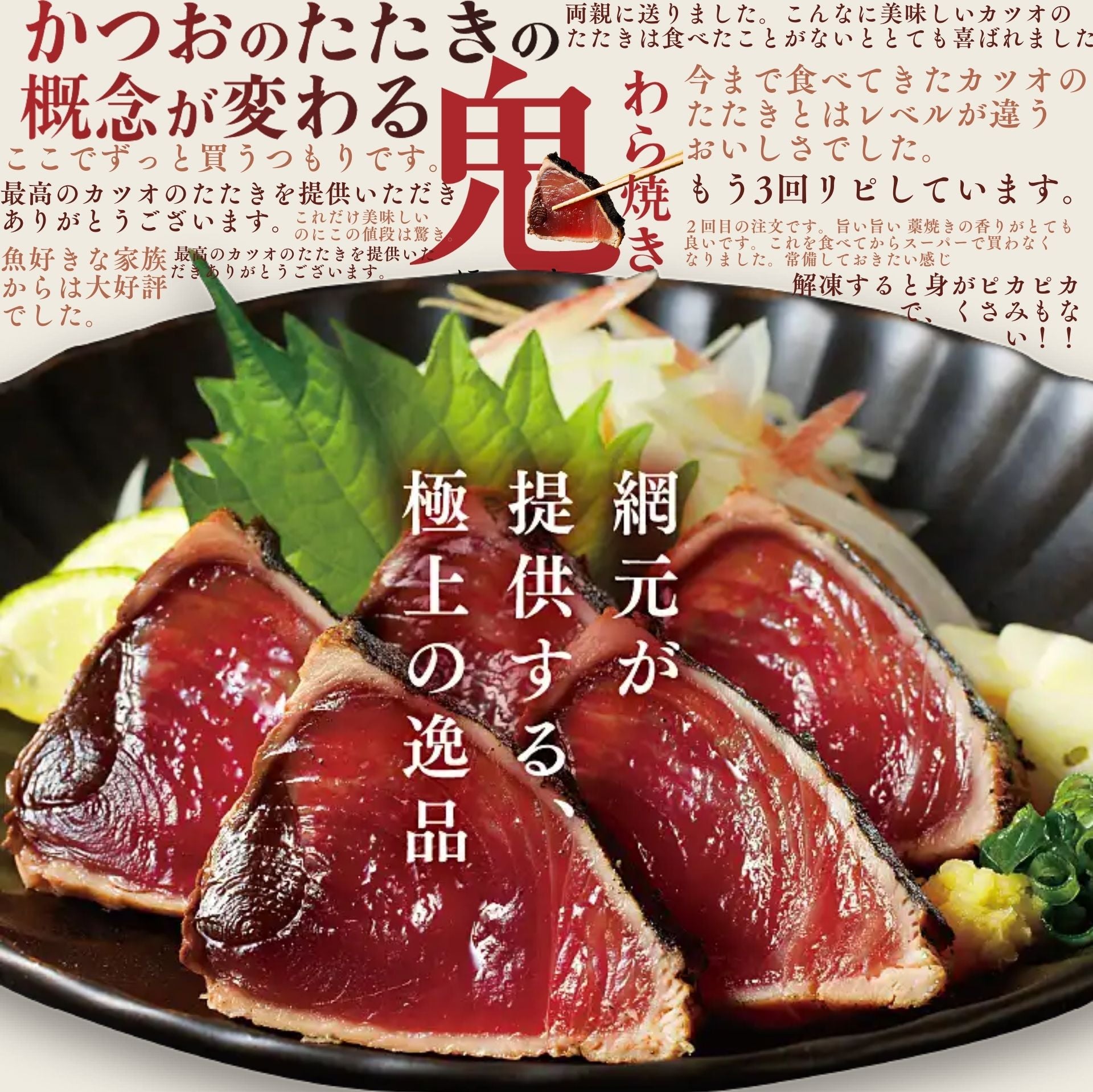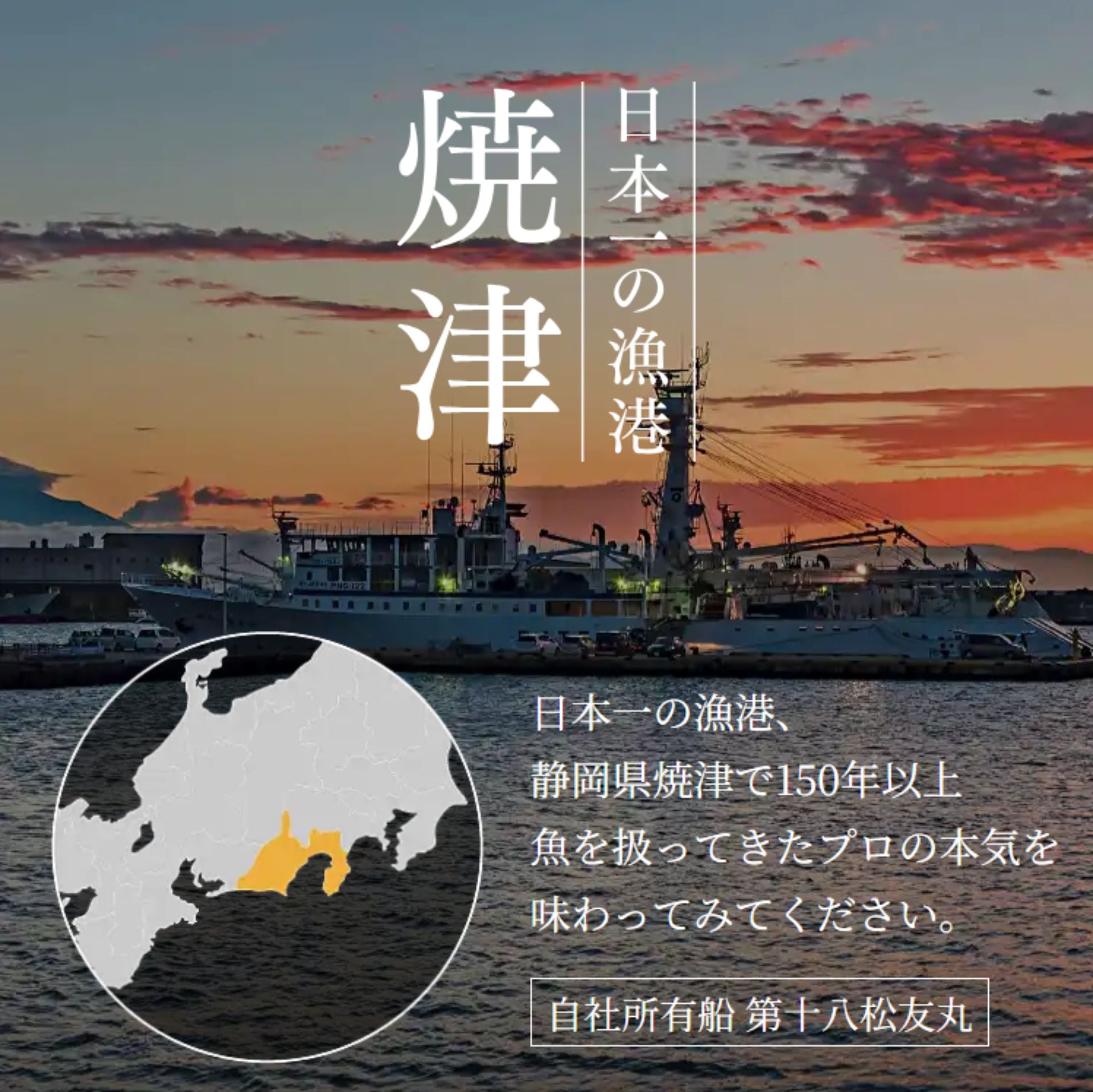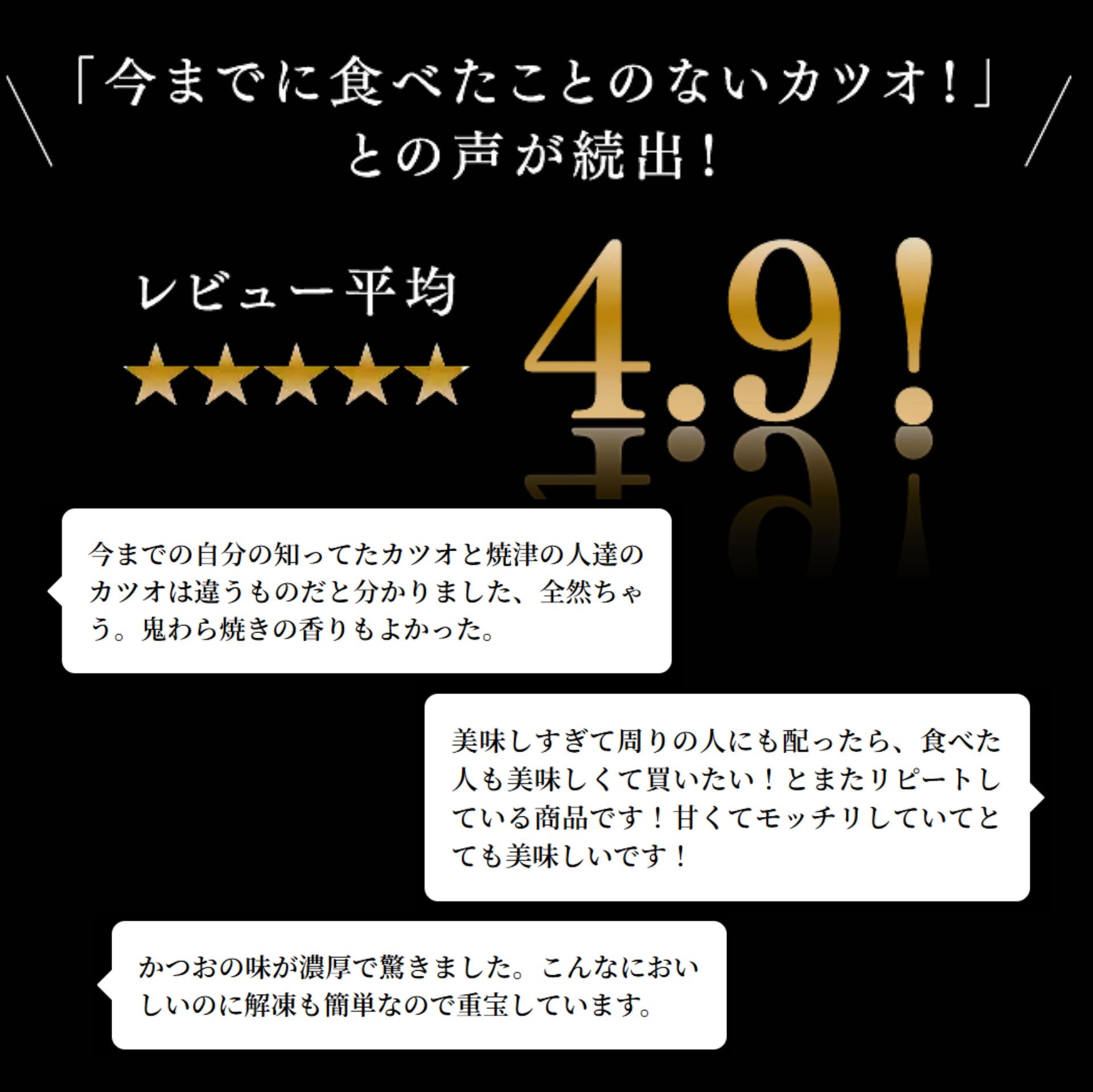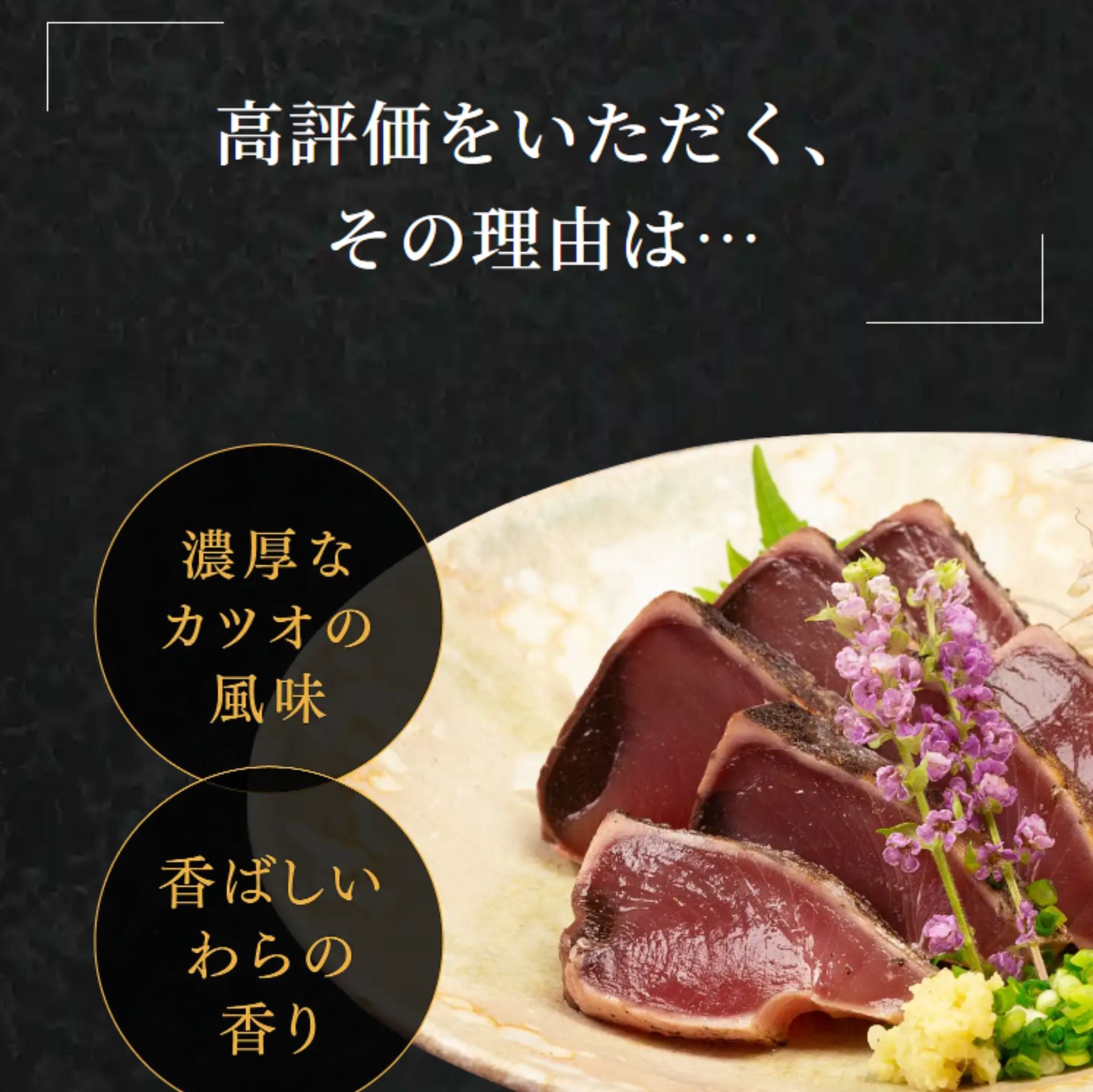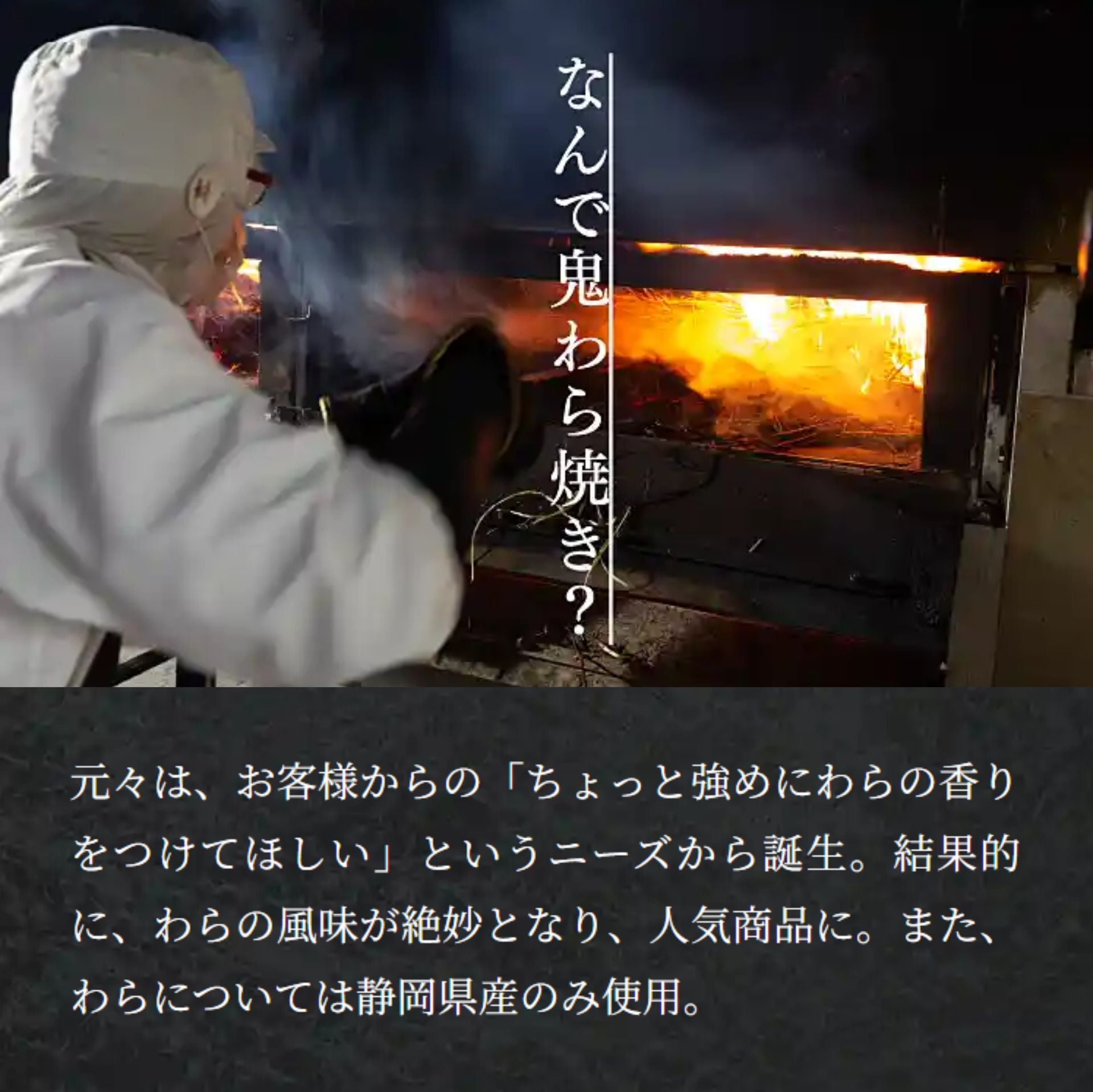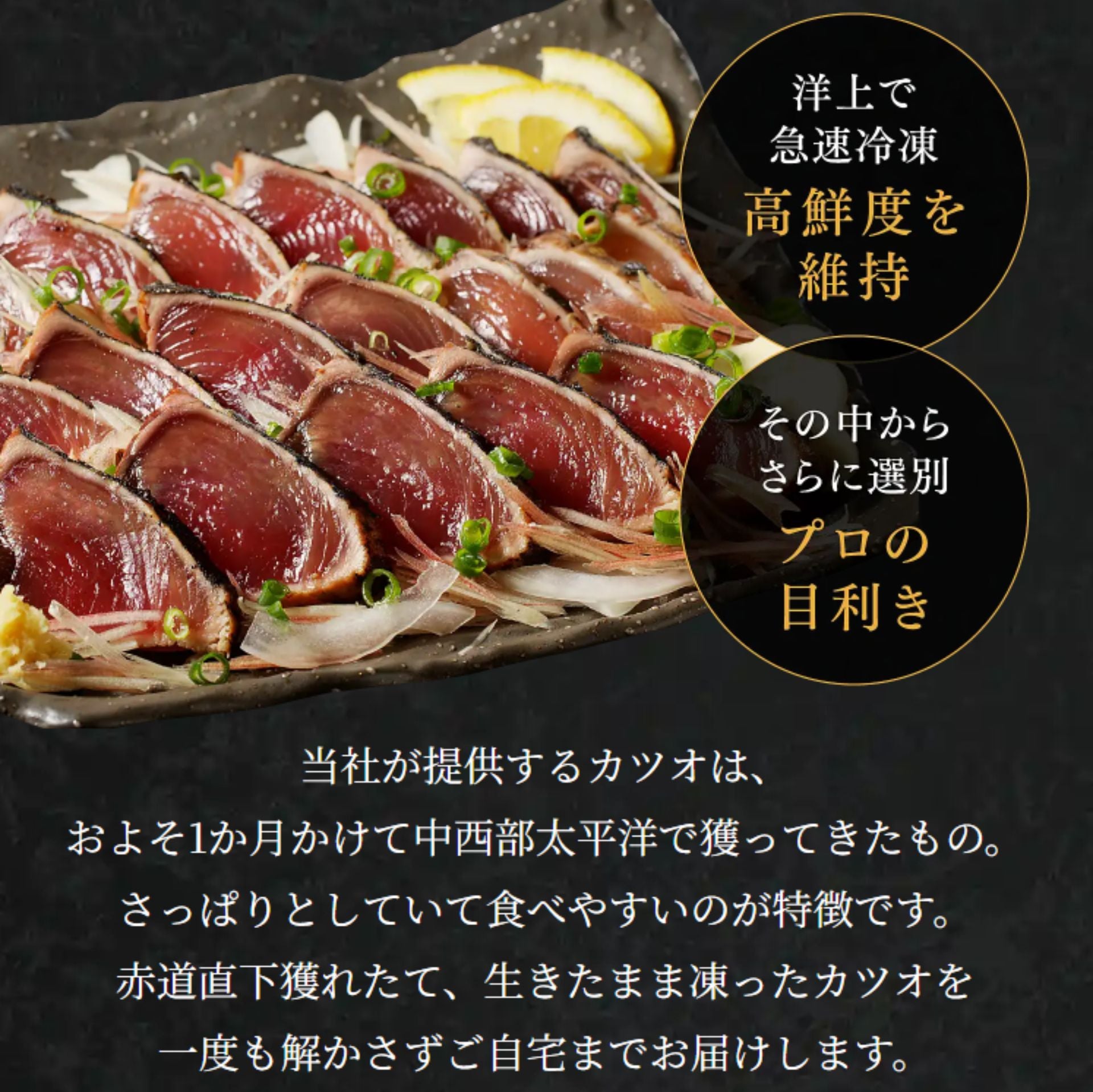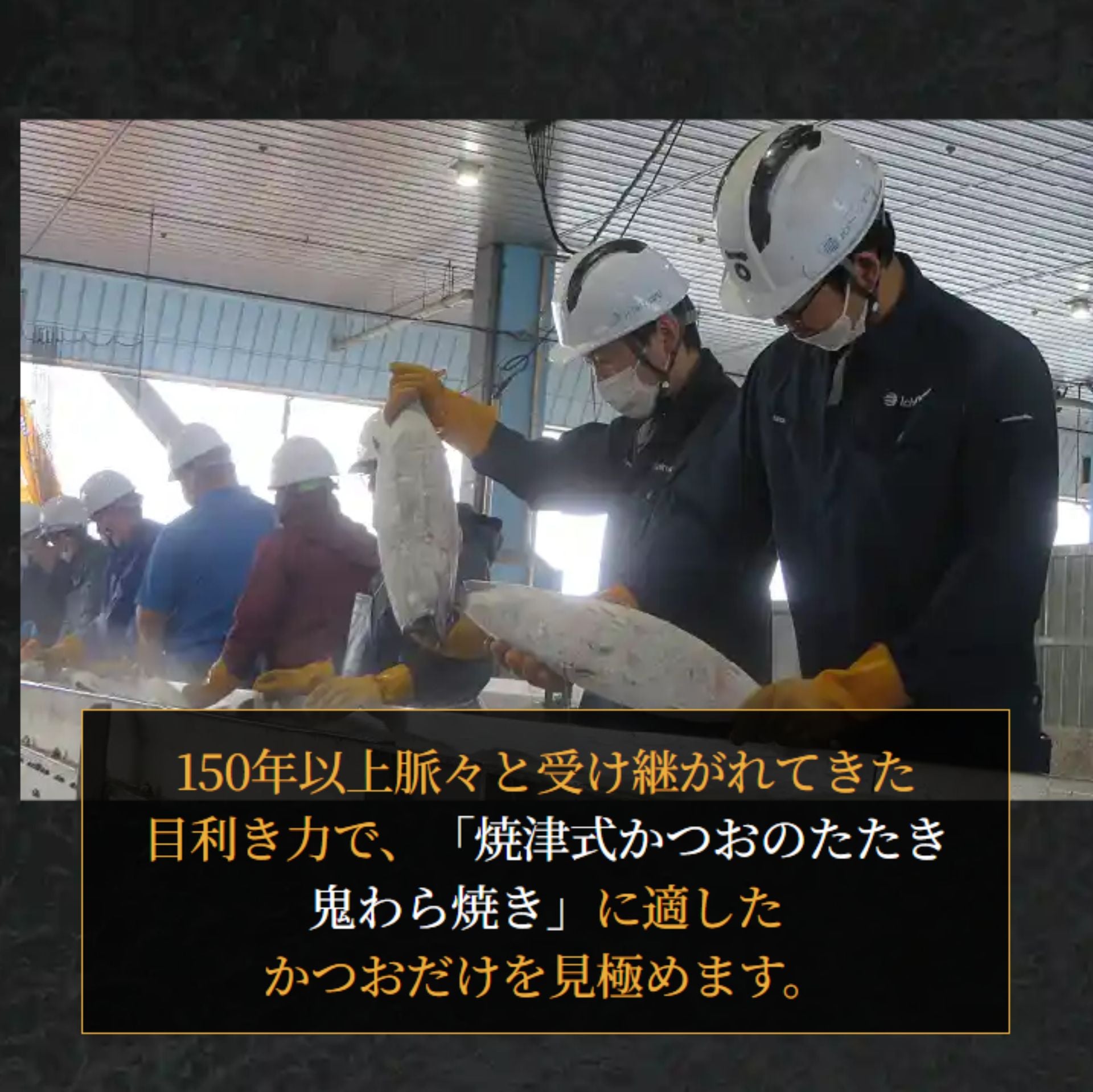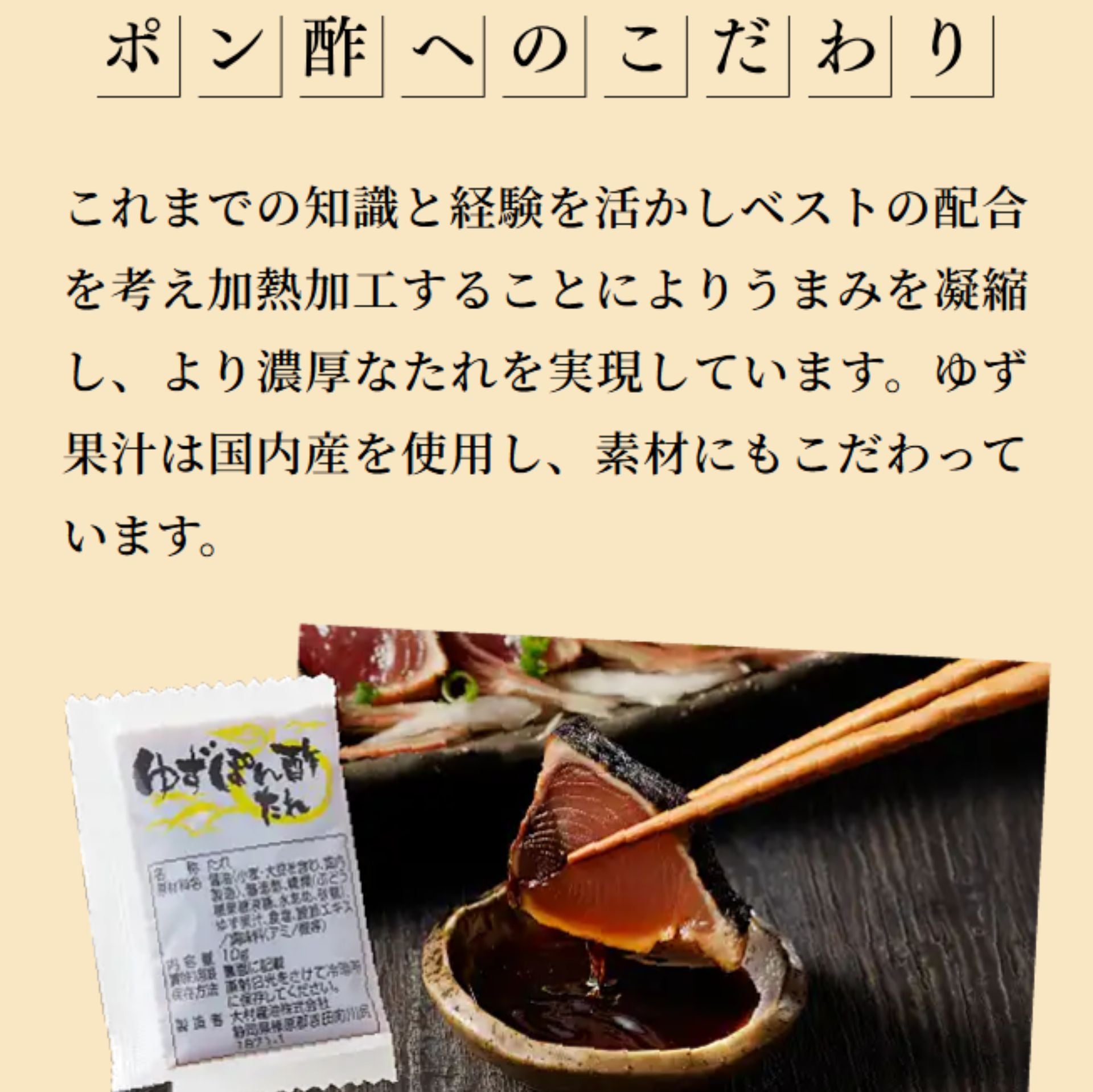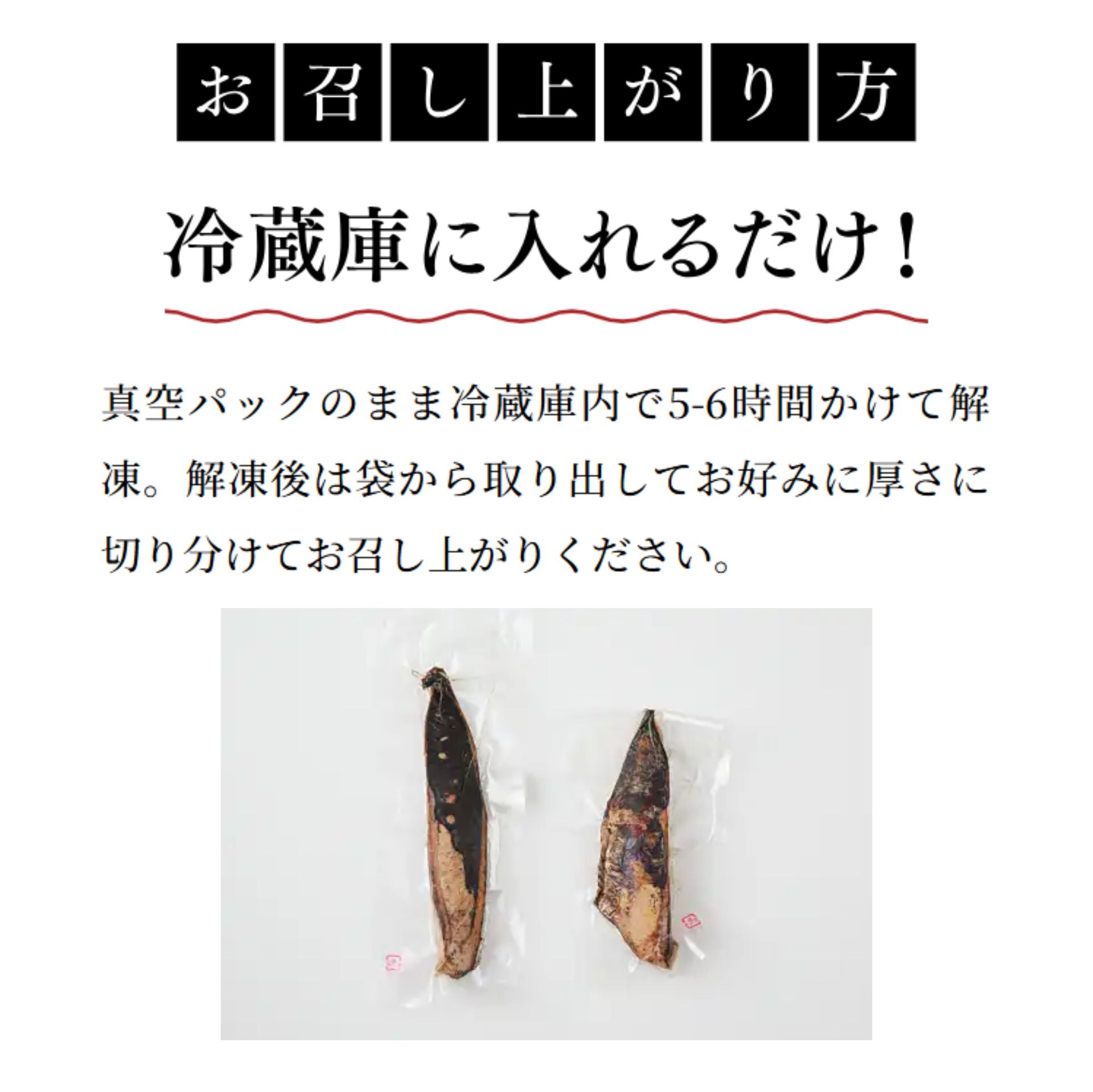鰹節の原型である「煮堅魚」と「堅魚煎汁」とは。

鰹節の原型である「煮堅魚」と「堅魚煎汁」は奈良時代に生まれたと伝えられています。
焼津の海で獲れた鰹は、保存性と高めるため、堝型(なべがた)土器と呼ばれる大きな土器を用い、竈で煮込んでいたと推測されます。各所で発掘されているこの土器は、通常のものより口が広く、大きな食材を煮込むのに適していたようです。海水で煮込み、塩分を含ませることで腐敗を防ぎ、保存に適した状態へと加工されたのではないかと考えられます。
また、煮上げた鰹は、焼津の海風を活かして干されていたと考えられます。まず干し台に並べて日光と風による自然乾燥を行い、水分が抜けて鰹が硬くなるとさらに乾燥を促すため、縄で結び、吊るして干すようなこともあったのではと推測されます。この工程により保存性が一層高まり、長期間の保管や持ち運びが可能な状態へと仕上げられました。
「煮堅魚」と「堅魚煎汁」の再現
このプロジェクトでは、古代の製法を再現し、「煮堅魚」と「堅魚煎汁」を作っています。海水で煮るという製法を再現するため、海水と同じ濃度の塩水で煮たあとに、乾燥させて仕上げ、削り節などへ加工をしております。